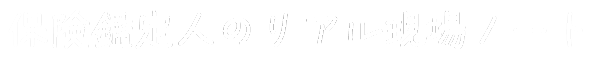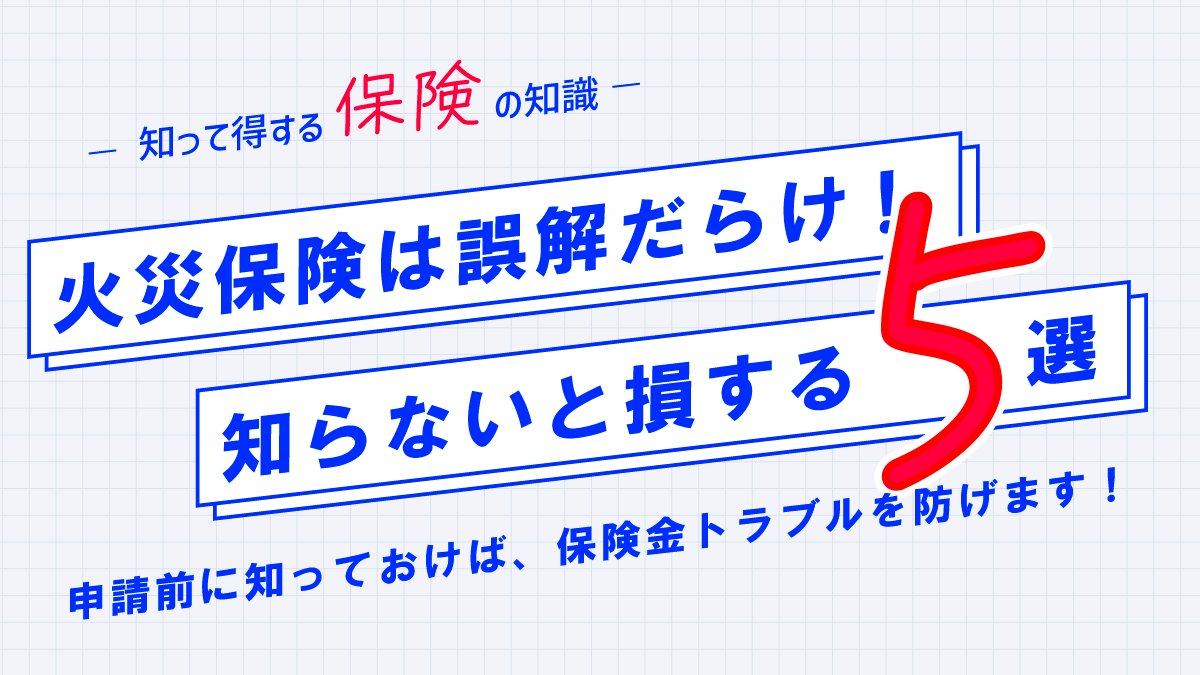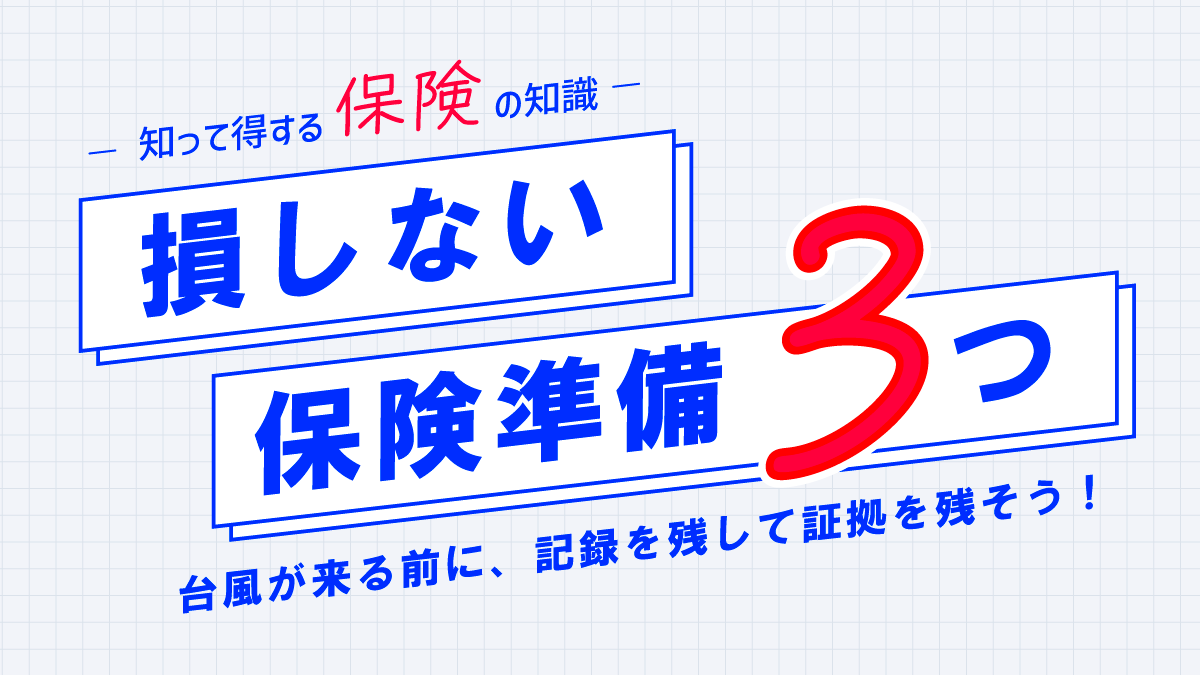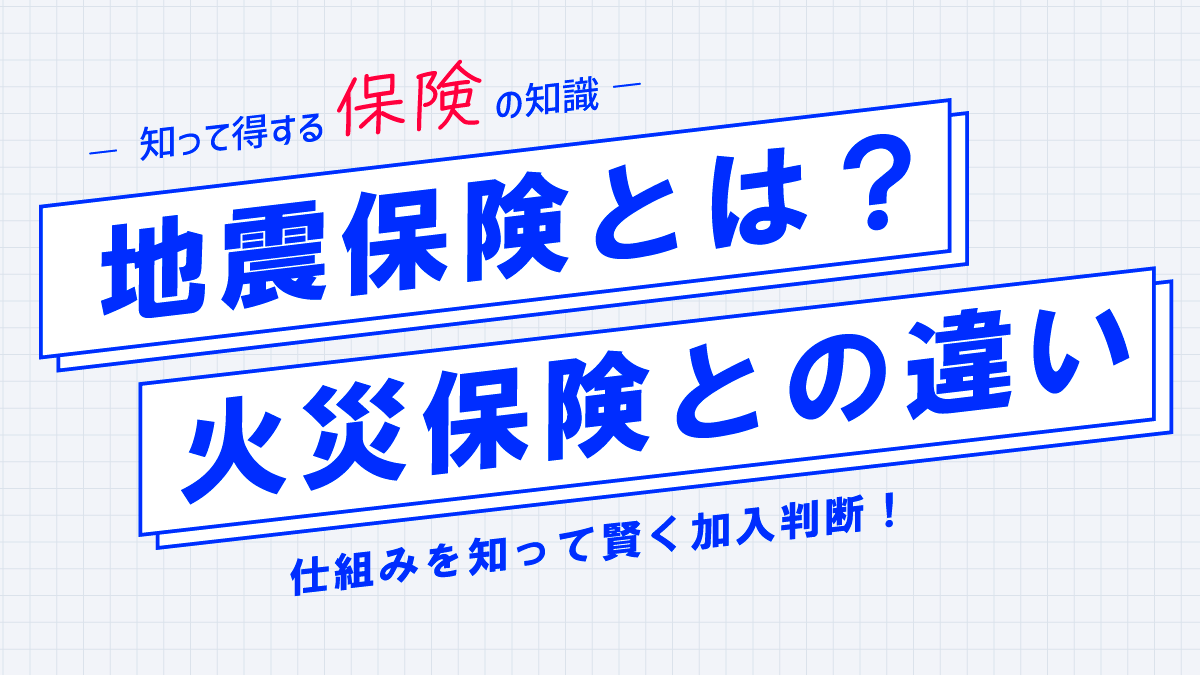火災保険は、多くの人が加入しているにもかかわらず、正しく理解されていないことがとても多い保険です。
現場で鑑定をしていると、「これって保険で直せないの?」「こんなときも申請できるの?」といった質問を本当によくいただきます。
そこで今回は、実際の現場でよく耳にする「誤解」を5つにまとめ、損害保険登録鑑定人の目線でわかりやすく解説していきます。
誤解①:「全損にならないと保険金は出ない」
これはとても多い誤解です。
火災保険は「全壊」しなくても、一部損害でも補償される仕組みになっています。たとえば…
- 台風で屋根の一部が飛んだ
- 強風でカーポートが壊れた
- 物を落として床に傷が入った
といったケースでも、適用対象になる可能性があります。
✅ 重要なのは「損害が保険の補償範囲に入るかどうか」
❌ 被害の規模が大きいかどうかではありません。
誤解②:「地震被害も火災保険でカバーできる」
火災保険は「地震による損害」は基本的に対象外です。
地震で発生した損害を補償するには、地震保険の加入が必要になります。
たとえば「地震で屋根瓦がずれて、雨漏りした」というケースでは、火災保険だけでは支払い対象にならない可能性が高いです。
👉 火災保険と地震保険はセットで検討することが大切です。
誤解③:「自己負担なしで必ず満額支払われる」
実際には、火災保険の中に「免責額(自己負担)」が発生するものがあります。
契約によっては数万円~10万円程度の自己負担が設定されていることもあり、被害額が免責額を下回ると保険金が出ないことがあります。
基本的に、損害の認定金額 – 免責額 = お支払い金額 となります。
また、査定の結果、見積金額=認定金額になるとは限りません。
損害の原因や劣化状態によっては、減額されるケースもあります。
👉 保険証券で免責額を事前に確認しておくと安心です。
誤解④:「保険を使うと等級が上がって保険料が高くなる」
自動車保険とは違い、火災保険には等級制度はありません。
そのため、「申請したら保険料が上がる」ということは基本的にはありません。
ただし、同じ場所での複数回申請は不正請求が増える背景もあり、保険会社のチェックは年々厳しくなっています。
過去の案件についても記録が残っているので、同じ損害内容と思われる場合については、過去の損害は修繕されているか、新しい損害かなど詳しく調べさせていただいています。
👉 「迷ったら申請しない」ではなく、「まずは相談」が正解です。
誤解⑤:「申請は業者に任せた方がスムーズ」
最近は、SNSや訪問営業などで「保険金が簡単におりる」「自己負担ゼロでリフォームできる」といった文言を使う業者も増えています。
しかし中には、
- 保険の内容を誤解させる
- 実際には対象外の修理を請求する
- 高額な手数料を請求する
などの悪質なケースが増えていますあります。
最近では、
「鑑定人は保険会社の味方だから、あなたの味方にはならない」
「何も知らない人が申請すると損しますよ!」
といった声をかけられ、不安になったという相談を受けることがあります。
確かに、保険金請求の流れはわかりにくく、専門用語も多いので、そう言われると不安になるのも無理はありません。
でも実際、鑑定人は“保険会社の味方”ではなく、損害を客観的に判断する中立の立場です。
むしろ「正しく申請していれば、きちんと補償されるように記録・調査を行う」のが仕事です。
👉 一方で、悪質な仲介業者に依頼してしまうと、
- 実態と合わずに支払いが遅れる
- トラブルになって審査が長引く
…といったケースも少なくありません。
📝 だからこそ、不安なときはまず代理店や保険会社に直接相談するのがいちばん安全です。
実際に、それが一番早く・スムーズに保険金が支払われるパターンも多いです。
📝 わからないときは、まず代理店や保険会社に直接相談するのが一番安全です。
まとめ|誤解をなくすことが、いざという時の「差」になる
- 火災保険は一部損害でも支払い対象になる
- 地震被害は対象外(地震保険が必要)
- 免責額や補償内容の確認が重要
- 等級制度はないが、使い方には注意
- 業者任せはトラブルのもとになることも
被害に遭ったときに損をしないためには、「事前の理解」と「正確な申請」が大切です。
もし迷ったときは、業者ではなく、まず代理店や保険会社に相談することをおすすめします。
✅ この記事のポイント
- 火災保険は「知らなかった」で損するケースが多い
- 申請の基本を理解するだけで大きな差が出る
- わからないときは公式ルートに頼るのが安心